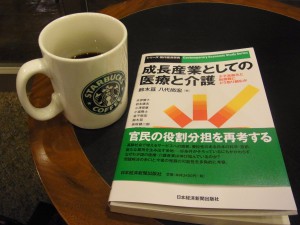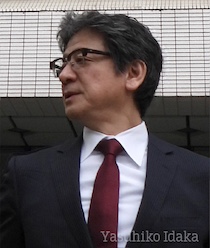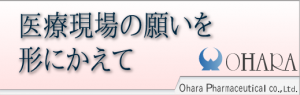Posted on 12月 12th, 2011 by IDAKA
 後発医薬品の使用促進が思ったように進んでいない―。ってことで、12年度薬価制度改革で、長期収載品(後発品がある先発品)薬価の追加引き下げが決定的になりました。医療費抑制のために、後発品使用促進を提言したのに、全然、進んでいない。それなら、後発品と競合関係にある長期収載品の薬価を下げて医療費を削る。という“荒療法”です。製薬業界は「各社に与えるダメージが大きい」と抵抗していますが、財務省は冷ややか。「(長期収載品の追加引き下げで、経営ダメージがあるというのは)本当なんでしょうか?もしあるというなら、その企業は、後発品使用促進が政府目標通り進んでいたら、どうなっていたんでしょうか?」(新川浩嗣主計官)。要するに、後発品使用促進をやるか、長期収載品の追加引き下げをやるか。選択肢は2つに1つ。どちらにせよ先発企業への影響はそれほど変わらないはず。それなのに、なぜ長期品の追加引き下げだけに、抵抗するのか?それとも、なんですか?政府が掲げた後発品使用促進そのものにも、実は反対してるんですか?本音を言えばまずいから黙っているけど。本当はやる気ないんですか?国策に、反旗を翻すのですか?と。。そう問うているわけです。きっつーい一言です。【この辺りの詳細は、今週発売の医薬経済12月15日号に書きましたので、是非、ご一読を。⇒http://www.risfax.co.jp/product/iyaku.html】近々、最終的な追加引き下げ率がはっきり決まります。
後発医薬品の使用促進が思ったように進んでいない―。ってことで、12年度薬価制度改革で、長期収載品(後発品がある先発品)薬価の追加引き下げが決定的になりました。医療費抑制のために、後発品使用促進を提言したのに、全然、進んでいない。それなら、後発品と競合関係にある長期収載品の薬価を下げて医療費を削る。という“荒療法”です。製薬業界は「各社に与えるダメージが大きい」と抵抗していますが、財務省は冷ややか。「(長期収載品の追加引き下げで、経営ダメージがあるというのは)本当なんでしょうか?もしあるというなら、その企業は、後発品使用促進が政府目標通り進んでいたら、どうなっていたんでしょうか?」(新川浩嗣主計官)。要するに、後発品使用促進をやるか、長期収載品の追加引き下げをやるか。選択肢は2つに1つ。どちらにせよ先発企業への影響はそれほど変わらないはず。それなのに、なぜ長期品の追加引き下げだけに、抵抗するのか?それとも、なんですか?政府が掲げた後発品使用促進そのものにも、実は反対してるんですか?本音を言えばまずいから黙っているけど。本当はやる気ないんですか?国策に、反旗を翻すのですか?と。。そう問うているわけです。きっつーい一言です。【この辺りの詳細は、今週発売の医薬経済12月15日号に書きましたので、是非、ご一読を。⇒http://www.risfax.co.jp/product/iyaku.html】近々、最終的な追加引き下げ率がはっきり決まります。
で、写真はさいたま市「市民の森・見晴公園」。よく晴れた休日、しばし森林浴でリラックス。いくつもの木が寄せ集まって、風や光と、みごとに調和した美しいシルエットを造っています。向こう側から、午後の太陽がまぶしい光を発しています。平和な風景。いよいよ年の瀬です。みなさま、お体に気を付けて。忙しいながら、楽しい日々をお過ごしください(^.^)/~~~
Posted on 12月 8th, 2011 by IDAKA
12月8日。きょうって何の日?第二次世界大戦が始まった日(1941年)。米国のアイゼンハワー大統領が国連総会で、原子力の平和利用を訴えた日(1953年)。で、己(オノレ)の兄貴、ジョン・レノンの命日(1980年)。んでもって、2011年、己が講演する日。天国の兄貴ぃーっ!光栄ですぜえーっ!拝。http://www.utobrain.co.jp/seminar/20111208/。
Posted on 12月 5th, 2011 by IDAKA
 11年9月分の取引を対象にした薬価調査結果。薬価と、納入価の乖離率は、前回(09年9月)同様8.4%ですって。「大手医薬品卸の利益が前年度と比べてかなり大きく落ち込んでいるのに、乖離率が前回と同じってなんかおかしくないですか?」。厚労省保険局医療課が開いた記者ブリーフイングで、平成の武士(もののふ)、半田良太くんが、事務局に詰め寄っていましたが、ホント、不可解!!。首都圏だけでなく、各地方の卸関係者に話を聞けば、一人残らず、「相当広がっている」と言っていたのに。。「価格の高い新薬創出加算対象品のしわ寄せを食って、確かに長期収載品価格が大きく下落した。しかし、新薬創出加算の対象品の取引数量が相当、伸びたから、加重平均では、前回と同様になった」(卸幹部)。そんな説明もありますが、薬価調査結果は、このところ毎回、腑に落ちない数値が出てきます。民間卸業者の協力で実施しているので、正式な行政調査ではなく、情報公開の対象にもならない。だから、言われた通り受け止めるしかないんですが・・・。いやはや何とも。中医協では、さずがに「一体、妥結率はどのくらいなんだ」「メーカーが後から卸に払うボリュームディスカウントは反映しているのか」という質問が出ました。妥結率は「78.1%(ということは21.9%未妥結)」、「事後のディスカウントは反映していない」との回答でした。その昔、今は亡き、健保連の下村健氏が言っていたことを思い出します。「こんな妥結率ではだめだ。とりあえず、この結果で暫定的に薬価を改定するが、100%妥結したら、もう一回調査して、暫定薬価を修正しろ」。至って正論ですわね 。
11年9月分の取引を対象にした薬価調査結果。薬価と、納入価の乖離率は、前回(09年9月)同様8.4%ですって。「大手医薬品卸の利益が前年度と比べてかなり大きく落ち込んでいるのに、乖離率が前回と同じってなんかおかしくないですか?」。厚労省保険局医療課が開いた記者ブリーフイングで、平成の武士(もののふ)、半田良太くんが、事務局に詰め寄っていましたが、ホント、不可解!!。首都圏だけでなく、各地方の卸関係者に話を聞けば、一人残らず、「相当広がっている」と言っていたのに。。「価格の高い新薬創出加算対象品のしわ寄せを食って、確かに長期収載品価格が大きく下落した。しかし、新薬創出加算の対象品の取引数量が相当、伸びたから、加重平均では、前回と同様になった」(卸幹部)。そんな説明もありますが、薬価調査結果は、このところ毎回、腑に落ちない数値が出てきます。民間卸業者の協力で実施しているので、正式な行政調査ではなく、情報公開の対象にもならない。だから、言われた通り受け止めるしかないんですが・・・。いやはや何とも。中医協では、さずがに「一体、妥結率はどのくらいなんだ」「メーカーが後から卸に払うボリュームディスカウントは反映しているのか」という質問が出ました。妥結率は「78.1%(ということは21.9%未妥結)」、「事後のディスカウントは反映していない」との回答でした。その昔、今は亡き、健保連の下村健氏が言っていたことを思い出します。「こんな妥結率ではだめだ。とりあえず、この結果で暫定的に薬価を改定するが、100%妥結したら、もう一回調査して、暫定薬価を修正しろ」。至って正論ですわね 。
で、写真は中医協会場となったグランドアーク半蔵門ホテルのロビー前で。午前7時頃。クリスマスツリーとイルミネーションを下から見上げるように撮りたくて、一瞬、床に寝転んで撮りました。しかし、その、あられもない恥ずかしい己(オノレ)の姿を、ちょっと離れていたところから、医薬経済の市川くんが激写していました。「おいおい君ぃ。困るなあ。スターを勝手に撮っちゃだめではないか。事務所も通さずしてから。失敬な。まうっ!」とか言って、市川くんに撮った写真を見せてもらったら、かぁーなり怪しい。不審者そのものでした(笑)どっかで公開されないか?ビクビクもんです。しかし、本人に「公開しないでね」とか言うと、返って、弱みに付け込まれる。きっと足元を見て「口止め料」か、何か、要請してくるに違いない。なんで、我慢して黙ってる。しばらく不安で眠れないかも。ダハッ(笑)
Posted on 11月 28th, 2011 by IDAKA
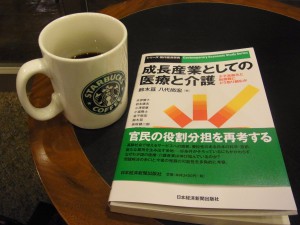 元万有製薬(現MSD)の社長、会長を務めた長坂健二郎氏が共同執筆された「成長産業としての医療と介護」(日本経済新聞出版社、税抜き2400円)が発刊されました。昨年も、東洋経済新報社から「日本の医療制度」という壮大なテーマの著作を発刊され、読んだら、ものすごく斬新な発想で現行制度を批判し、改善策を提案されていた。こりゃ一回お会いするしかないだろう、ってなことで、今年9月にインタビューさせていだきました。【医薬経済10月15日号掲載⇒http://www.risfax.co.jp/product/iyaku.html】そして、今回、共著という形で新本を発刊。ご引退されて、数年経ちますが、現状認識や将来予測、改善策に関するお話は、きわめて論理的で、シャープ。現役実務者にはない、柔軟な発想で、大胆かつ斬新な提案を打ち出しております。長坂さんは第5章「日本の医薬品産業をどう発展させるか」を担当、医薬品の許認可制度、薬価制度を根本から問い直す新たな提案を披露しています。長坂さん曰く、「近い将来、自動車、電機などに並ぶ、日本のリーディング産業に育って欲しいとの願いを込めて本章を書きました」。是非、ご一読をお勧めいたします。
元万有製薬(現MSD)の社長、会長を務めた長坂健二郎氏が共同執筆された「成長産業としての医療と介護」(日本経済新聞出版社、税抜き2400円)が発刊されました。昨年も、東洋経済新報社から「日本の医療制度」という壮大なテーマの著作を発刊され、読んだら、ものすごく斬新な発想で現行制度を批判し、改善策を提案されていた。こりゃ一回お会いするしかないだろう、ってなことで、今年9月にインタビューさせていだきました。【医薬経済10月15日号掲載⇒http://www.risfax.co.jp/product/iyaku.html】そして、今回、共著という形で新本を発刊。ご引退されて、数年経ちますが、現状認識や将来予測、改善策に関するお話は、きわめて論理的で、シャープ。現役実務者にはない、柔軟な発想で、大胆かつ斬新な提案を打ち出しております。長坂さんは第5章「日本の医薬品産業をどう発展させるか」を担当、医薬品の許認可制度、薬価制度を根本から問い直す新たな提案を披露しています。長坂さん曰く、「近い将来、自動車、電機などに並ぶ、日本のリーディング産業に育って欲しいとの願いを込めて本章を書きました」。是非、ご一読をお勧めいたします。
写真は長坂さんの共著と、スタバのカップ。皆さま。寒くなってきました。ご自愛ください。
Posted on 11月 24th, 2011 by IDAKA
 いやあ~22日の行政刷新会議の事業仕分け。先発品と後発品そして市販薬類似品の問題、かなり踏み込んだ提言を打ち出しましたね。【RISFAX11月24日号詳報⇒http://www.risfax.co.jp/】後発品使用促進どころか、それを飛び越えて、保険給付は後発品薬価まで、それ以上は自己負担にすべきだって。これは、かつて一度、白紙撤回になった参照価格制度そのものじゃないですかあ!みなさんよく「事業仕分けに法的拘束力はない」と言われます。しかし、たかが事業仕分け、されど事業仕分けですぜ。世の中の空気はしっかりリードしています。12年度改定、どうも長期収載品(特許が切れた先発品)の薬価引き下げは、避けられそうもない気配が漂ってきました。それから市販薬類似品、ビタミン剤は、将来、保険給付になんらかの制限が加えられるでしょう。事業仕分けの委員の発言には、製薬業界の胸をえぐる発言が多々ありました。先発と後発品の論議では「おんなじ物なのに、薬価が違うのはおかしい。公的保険制度の枠組みで考えれば、薬価の高い先発品を使った人は、薬価の安い後発品を使った人に負担を押しつけていることになる。どうしても先発品を使いたいなら、その差額は自己負担にすべきだ」、市販薬類似品では「薬局で買うより病院でもらった方が安いからと言って、どんどん使っていると、医療保険が窮迫し、結局、保険料を上げなければならなくなる。知らず知らずのうちに、自分で自分の首を絞める悪い仕組みだ」などなど。でも、正論ですよね。これ。さて中医協がどう反応するか。
いやあ~22日の行政刷新会議の事業仕分け。先発品と後発品そして市販薬類似品の問題、かなり踏み込んだ提言を打ち出しましたね。【RISFAX11月24日号詳報⇒http://www.risfax.co.jp/】後発品使用促進どころか、それを飛び越えて、保険給付は後発品薬価まで、それ以上は自己負担にすべきだって。これは、かつて一度、白紙撤回になった参照価格制度そのものじゃないですかあ!みなさんよく「事業仕分けに法的拘束力はない」と言われます。しかし、たかが事業仕分け、されど事業仕分けですぜ。世の中の空気はしっかりリードしています。12年度改定、どうも長期収載品(特許が切れた先発品)の薬価引き下げは、避けられそうもない気配が漂ってきました。それから市販薬類似品、ビタミン剤は、将来、保険給付になんらかの制限が加えられるでしょう。事業仕分けの委員の発言には、製薬業界の胸をえぐる発言が多々ありました。先発と後発品の論議では「おんなじ物なのに、薬価が違うのはおかしい。公的保険制度の枠組みで考えれば、薬価の高い先発品を使った人は、薬価の安い後発品を使った人に負担を押しつけていることになる。どうしても先発品を使いたいなら、その差額は自己負担にすべきだ」、市販薬類似品では「薬局で買うより病院でもらった方が安いからと言って、どんどん使っていると、医療保険が窮迫し、結局、保険料を上げなければならなくなる。知らず知らずのうちに、自分で自分の首を絞める悪い仕組みだ」などなど。でも、正論ですよね。これ。さて中医協がどう反応するか。
で、写真は東京霞ヶ関午前6時45分。日比谷公園近くから、国会議事堂方面を眺める。まだ、ほとんど人がいない(笑)サブ!もうコートが要りますね。みなさん、風邪にご注意ください。
Posted on 11月 21st, 2011 by IDAKA
 製薬企業各社は海外戦略のターゲットを、これまでの欧米中心から、発展著しいBRICS(ブリックス)に移しています。当然のことながら、成否のカギは、日本本社が、いかに上手に拠点業務をオペレーションするかです。ところがBRICS諸国。戦後日本が親しんできた欧米とは、価値観、文化、政治体制が全く異なる。ましてやロシア、中国なんて、共産圏です。「いいものを造れば、うまくいく」という単純なものではないでしょう。各社のマネジメント手腕が注目されるところです。
製薬企業各社は海外戦略のターゲットを、これまでの欧米中心から、発展著しいBRICS(ブリックス)に移しています。当然のことながら、成否のカギは、日本本社が、いかに上手に拠点業務をオペレーションするかです。ところがBRICS諸国。戦後日本が親しんできた欧米とは、価値観、文化、政治体制が全く異なる。ましてやロシア、中国なんて、共産圏です。「いいものを造れば、うまくいく」という単純なものではないでしょう。各社のマネジメント手腕が注目されるところです。
で、写真は代々木公園。20日、晴れやかな日曜日、テレっとそぞろ歩き。屋台がすっごい。
Posted on 11月 17th, 2011 by IDAKA
 昨日の中医協総会。ノバルティスの希少疾病用薬イラリスの薬価収載を了承しませんでした。 【RISFAX11月17日号詳報⇒https://www.risfax.co.jp/】そもそも総会の開始の仕方が、おかしかった。報告者である薬価算定組織の長瀬隆英委員長(東大大学院教授)の“都合”で、薬価専門部会を中断して無理やり総会を割り込ませた。しかも、その時、すでに時計の針は11時30分近くを指していたのに、森田朗会長(東大大学院教授)が長瀬委員長の“都合”に配慮して「審議時間は11時50分までしかありません」と委員に言ったんですよ。薬事承認した医薬品は基本的に薬価収載するのが通例だとしても、中医協総会は、単なる追認機関ですか?曲がりなりにも、新薬を保険で認めるか否かを審議する大事な場ではないのですか?20分で、9成分10品目を審議しようなんて、手抜きもいいところですよ。いくら東大大学院教授で、忙しいからと言っても、看過できない。結局、嘉山孝正委員(国立がん研究センター理事長)が、イラリスに関する厚労省の説明を「官僚的」と撥ねつけ、次回の総会で再度、説明するよう要請。さらに、安達秀樹委員(京都府医師会副会長)が、旭化成ファーマの「テリボン皮下注」に「ピーク時の市場規模予測が2.5万人になっているが、こんな小さくおさまるだろうか」と疑義を挟んで、森田会長や、長瀬委員長が意図した“シャンシャン総会”にはなりませんでした。終わった時間も正午を回っていました(笑)。中医協は審議の場、めくら判(失礼)を捺す場所ではありません。これぞ、あるべき姿だと思います。
昨日の中医協総会。ノバルティスの希少疾病用薬イラリスの薬価収載を了承しませんでした。 【RISFAX11月17日号詳報⇒https://www.risfax.co.jp/】そもそも総会の開始の仕方が、おかしかった。報告者である薬価算定組織の長瀬隆英委員長(東大大学院教授)の“都合”で、薬価専門部会を中断して無理やり総会を割り込ませた。しかも、その時、すでに時計の針は11時30分近くを指していたのに、森田朗会長(東大大学院教授)が長瀬委員長の“都合”に配慮して「審議時間は11時50分までしかありません」と委員に言ったんですよ。薬事承認した医薬品は基本的に薬価収載するのが通例だとしても、中医協総会は、単なる追認機関ですか?曲がりなりにも、新薬を保険で認めるか否かを審議する大事な場ではないのですか?20分で、9成分10品目を審議しようなんて、手抜きもいいところですよ。いくら東大大学院教授で、忙しいからと言っても、看過できない。結局、嘉山孝正委員(国立がん研究センター理事長)が、イラリスに関する厚労省の説明を「官僚的」と撥ねつけ、次回の総会で再度、説明するよう要請。さらに、安達秀樹委員(京都府医師会副会長)が、旭化成ファーマの「テリボン皮下注」に「ピーク時の市場規模予測が2.5万人になっているが、こんな小さくおさまるだろうか」と疑義を挟んで、森田会長や、長瀬委員長が意図した“シャンシャン総会”にはなりませんでした。終わった時間も正午を回っていました(笑)。中医協は審議の場、めくら判(失礼)を捺す場所ではありません。これぞ、あるべき姿だと思います。
で、写真は最寄駅、午前5時30分ごろの風景。16日の中医協薬価専門部会・総会を傍聴するため、早起きしました。寒ぶっ!このくらい早く行けば、かなり上位だろうと思っていたら、医薬経済の市川君と、グッチ(坂口君)は、すでに来ていました(笑)。ただ、平成の武士(もののふ)、半ちゃん(半田良太君)には、僅差で勝ったあー!うれぴーっ!(失礼、こんなのも傍聴の楽しみなのです)しかし、この日は会場が厚労省講堂で、席に余裕が・・。並ばなくてもは入れた模様。うーん、中医協傍聴は読みが難しい!
Posted on 11月 15th, 2011 by IDAKA
武田薬品がきょう15日から、服薬サポートプログラム「アドポート」を開始し、患者とダイレクトにつながる考えです。【詳細はRISFAX11年11月15日号⇒http://www.risfax.co.jp/】このプログラムは薬の飲み忘れを防ぐために、患者さんの希望時間に携帯電話にメールを配信するサービスです。登録は無料。患者が積極的に治療に参加し、主体的に治療を継続する、いわゆるアドヒアランスの向上が狙いです。せっかく薬を処方しても、患者が勝手に途中で、服薬を中止し、十分な治療効果が発揮できないケースが多いと言われます。米国では、これによって年間約1兆5000億円の医療費増が生じているというデータがあるそうです。武田薬品は「アドポート」の活用を呼び掛け、治療効果を高める考えです。IT全盛、ジョブズ教信者が席巻する世の中にあって、それに惑わされず、敢えて進化が行き着いた「携帯電話」を用いる“合理的姿勢”が武田らしい。プログラムの開発経費は4~5000万円、発想から、わずか4カ月で実用にこぎつけたというから、驚きです。さりとて武田も、上場株式会社。当然、収益に結びつけるマーケティング戦略があるはずです。患者とダイレクトにつながるというのが、キーのようで、こっちから情報を送信することもできますし、逆に受けることも可能です。使いようによっては、いろんなマーケティングデータを集積できるでしょう。ただ、少なくとも、このプログラムで、アドヒアランスが向上した患者は、治療効果が高まるので、いまより早く疾患が治る。そうすると、無駄な投薬が無くなる分、製薬企業にとっては収益減につながる可能性も予測されます。
で、画像はサブリナ・スターケの「サニーデイ」。気持ちの良い秋晴れの日に、何も考えずに、ただただ生きていることの幸せを噛みしめて散歩する時、掃除する時、家事をする時などに最適です。ではでは、みなさま素敵な一日をお過ごしください。
Posted on 11月 14th, 2011 by IDAKA
 後発医薬品の使用。なかなか進まないです。このままいくと12年度、数量ベースで30%以上という目標達成は、厳しい。そんな状況であるにもかかわらず、厚労省の武田俊彦政策統括官参事官は「30%以上の次は、さらに高いレベルの目標を設定する」と声高に叫んでいます。しかし、最近、改めてよく考えます。なぜ、後発品使用が進まないのか?そもそも後発品使用促進の狙いは何だったのか?そして、その狙いと施策は合致しているのか?と。。で、結論から言えば、使用が進まないのは、いまの価格と、ブランド力では、まだ後発品より先発品を使った方がいいと考える医師や患者が多いということでしょう。裏を返せば、いまの施策は、もう限界が来ている。狙いが医療費抑制であるならば、そろそろ施策を切り替える必要が出てきているんじゃないか。己(オノレ)はそう考えます。後発品は、各社努力によってジェネリックという通称で、国民に周知されるようになりました。かつてのように供給が急に途絶えたり、品質が不安定だったりすることもありません。良い意味で、十分、存在感を発揮している。だから、医療費抑制が狙いであるにもかかわらず、医療機関や保険薬局に「後発品を使え。使ったら金やるから」という、矛盾極まりない経済誘導策はもう終わりにした方がいい。で、どうするか?己は、先発品も後発品も同じ薬価にすればいいんじゃないかと考えます。そこで競争すればいい。そうなると、情報提供に力を入れる先発品は「医療機関や薬局に薬価差を出せないから、不利だ」という声が出るでしょう。でも、だったら出さなきゃいいじゃないですか。自分たちの製品を使ってもらえるところには、とことん情報提供する。その代わり薬価差は出さない。逆に、後発品は薬価差で勝負する。あるいは先発品に負けないように情報提供する。それでいいんじゃないでしょうか?特許が切れた先発品(長期収載品)と、後発品は、ライバル関係にあります。にもかかわらず、政府が片方だけを利するように、テコ入れするのは、おかしなことじゃないでしょうか?もう十分、後発品の知名度も信頼度も上がったんだから、後は先発品と後発品を同じ薬価にして、納入価(すなわち薬価差)と、情報提供と、信頼感を競い合い、医療現場、市場に委ねればいいのではないか。己は、そう考えます。
後発医薬品の使用。なかなか進まないです。このままいくと12年度、数量ベースで30%以上という目標達成は、厳しい。そんな状況であるにもかかわらず、厚労省の武田俊彦政策統括官参事官は「30%以上の次は、さらに高いレベルの目標を設定する」と声高に叫んでいます。しかし、最近、改めてよく考えます。なぜ、後発品使用が進まないのか?そもそも後発品使用促進の狙いは何だったのか?そして、その狙いと施策は合致しているのか?と。。で、結論から言えば、使用が進まないのは、いまの価格と、ブランド力では、まだ後発品より先発品を使った方がいいと考える医師や患者が多いということでしょう。裏を返せば、いまの施策は、もう限界が来ている。狙いが医療費抑制であるならば、そろそろ施策を切り替える必要が出てきているんじゃないか。己(オノレ)はそう考えます。後発品は、各社努力によってジェネリックという通称で、国民に周知されるようになりました。かつてのように供給が急に途絶えたり、品質が不安定だったりすることもありません。良い意味で、十分、存在感を発揮している。だから、医療費抑制が狙いであるにもかかわらず、医療機関や保険薬局に「後発品を使え。使ったら金やるから」という、矛盾極まりない経済誘導策はもう終わりにした方がいい。で、どうするか?己は、先発品も後発品も同じ薬価にすればいいんじゃないかと考えます。そこで競争すればいい。そうなると、情報提供に力を入れる先発品は「医療機関や薬局に薬価差を出せないから、不利だ」という声が出るでしょう。でも、だったら出さなきゃいいじゃないですか。自分たちの製品を使ってもらえるところには、とことん情報提供する。その代わり薬価差は出さない。逆に、後発品は薬価差で勝負する。あるいは先発品に負けないように情報提供する。それでいいんじゃないでしょうか?特許が切れた先発品(長期収載品)と、後発品は、ライバル関係にあります。にもかかわらず、政府が片方だけを利するように、テコ入れするのは、おかしなことじゃないでしょうか?もう十分、後発品の知名度も信頼度も上がったんだから、後は先発品と後発品を同じ薬価にして、納入価(すなわち薬価差)と、情報提供と、信頼感を競い合い、医療現場、市場に委ねればいいのではないか。己は、そう考えます。
で、写真は荻窪のバー。入口に、なかなかインパクトのあるオブジェが。有名な建築家が造ったもののようですが、詳細は分かりません。この日は前を通っただけで入りませんでした。しかし、このオブジェ。何かこっちに訴えてくるものがあります。今度、中に入ってバーボンをロックで頼んでみようかと。ではではみなさま、素敵な1週間をお過ごしください。
Posted on 11月 11th, 2011 by IDAKA
泉谷しげると、仲井戸麗市が中心になって「東日本の野菜を買って復興を応援しよう!」http://hibiya-live-marche.jp/というコンサートをやるらしい。でも、そーゆー単純な話じゃないだろ。バックは農水省、農協、そして、いまだナベツネ影響下にあって原発大好きなマスコミ読売新聞。お調子者にも、程がある。そこまで食い詰めたか。参加するミュージシャンは、みんな大政翼賛会。“反”体制ならぬ“従”体制。個人的には、タケカワユキヒデみたいな知的水準が高い人が参加していることがショックだが。ブーイングの極致。栗原清志(忌野清志郎)が知ったら、泣くだろう。動画はRCサクセッションの「あきれて物も言えない」。これは、泉谷しげるの蔭口に、清志が怒って作った曲。チャボもやっぱり清志がいないと駄目だ。歌詞はコチラ⇒http://music.goo.ne.jp/lyric/LYRUTND29131/index.html
 後発医薬品の使用促進が思ったように進んでいない―。ってことで、12年度薬価制度改革で、長期収載品(後発品がある先発品)薬価の追加引き下げが決定的になりました。医療費抑制のために、後発品使用促進を提言したのに、全然、進んでいない。それなら、後発品と競合関係にある長期収載品の薬価を下げて医療費を削る。という“荒療法”です。製薬業界は「各社に与えるダメージが大きい」と抵抗していますが、財務省は冷ややか。「(長期収載品の追加引き下げで、経営ダメージがあるというのは)本当なんでしょうか?もしあるというなら、その企業は、後発品使用促進が政府目標通り進んでいたら、どうなっていたんでしょうか?」(新川浩嗣主計官)。要するに、後発品使用促進をやるか、長期収載品の追加引き下げをやるか。選択肢は2つに1つ。どちらにせよ先発企業への影響はそれほど変わらないはず。それなのに、なぜ長期品の追加引き下げだけに、抵抗するのか?それとも、なんですか?政府が掲げた後発品使用促進そのものにも、実は反対してるんですか?本音を言えばまずいから黙っているけど。本当はやる気ないんですか?国策に、反旗を翻すのですか?と。。そう問うているわけです。きっつーい一言です。【この辺りの詳細は、今週発売の医薬経済12月15日号に書きましたので、是非、ご一読を。⇒http://www.risfax.co.jp/product/iyaku.html】近々、最終的な追加引き下げ率がはっきり決まります。
後発医薬品の使用促進が思ったように進んでいない―。ってことで、12年度薬価制度改革で、長期収載品(後発品がある先発品)薬価の追加引き下げが決定的になりました。医療費抑制のために、後発品使用促進を提言したのに、全然、進んでいない。それなら、後発品と競合関係にある長期収載品の薬価を下げて医療費を削る。という“荒療法”です。製薬業界は「各社に与えるダメージが大きい」と抵抗していますが、財務省は冷ややか。「(長期収載品の追加引き下げで、経営ダメージがあるというのは)本当なんでしょうか?もしあるというなら、その企業は、後発品使用促進が政府目標通り進んでいたら、どうなっていたんでしょうか?」(新川浩嗣主計官)。要するに、後発品使用促進をやるか、長期収載品の追加引き下げをやるか。選択肢は2つに1つ。どちらにせよ先発企業への影響はそれほど変わらないはず。それなのに、なぜ長期品の追加引き下げだけに、抵抗するのか?それとも、なんですか?政府が掲げた後発品使用促進そのものにも、実は反対してるんですか?本音を言えばまずいから黙っているけど。本当はやる気ないんですか?国策に、反旗を翻すのですか?と。。そう問うているわけです。きっつーい一言です。【この辺りの詳細は、今週発売の医薬経済12月15日号に書きましたので、是非、ご一読を。⇒http://www.risfax.co.jp/product/iyaku.html】近々、最終的な追加引き下げ率がはっきり決まります。