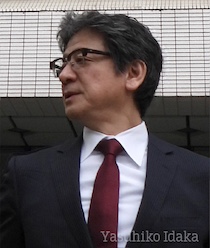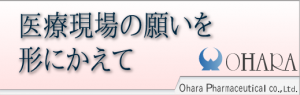※事実誤認があったため6日午後、一部修正しました。
※事実誤認があったため6日午後、一部修正しました。
武田薬品が糖尿病治療剤「リオベル配合錠LD」の製剤に誤って「リオベル配合錠HD」と刻印し、100包装品3000箱、500錠包装1500箱を自主回収しました。主成分であるピオグリタゾンの含有量がLDは、HDより少ないので、HDと思って使うと効果がマイルドに出てしまう可能性があるとのことです。回収した製剤は、全て廃棄するそうです。誠実な対応。日本では珍しくないですね。しかし、海外ではどうなのでしょうか?欧米は、それほど違いはないでしょうが、新興国の製薬企業は、医療機関に口頭で伝えることはしても、必ずしも回収までするかどうか。
「日本では錠剤の端がちょっと欠けていてもアウト。海外の企業からすればオーバークオリティだ」と、良く言われます。だから、海外、とくに新興国で、日本と同レベルの品質、製造管理をしていると、コスト高になって競争に勝てない。言葉は悪いのですが、一定のダウン・クオリティが必要になる。しかし、当然、医薬品ですからダウンしすぎると、これまた問題です。その微妙な機微を掴むセンサー機能が、日本企業各社にとってますます重要になるでしょう。
で、写真は上野公園の夜桜。今年もきれいに咲いておりました。東京の花見は今週一杯でお開きです。それではみなさん、充実した素敵な一週間をお過ごしください!
 ちょっと前の週刊新潮(3月26日号=特集「安倍内閣」大臣たちの持ち株リスト)で、塩崎恭久厚労大臣が、様々な業種の大手企業の株式をバランスよく保有していることを取り上げ、「相場巧者」と揶揄していました。
ちょっと前の週刊新潮(3月26日号=特集「安倍内閣」大臣たちの持ち株リスト)で、塩崎恭久厚労大臣が、様々な業種の大手企業の株式をバランスよく保有していることを取り上げ、「相場巧者」と揶揄していました。
安倍政権は14年秋、我々国民の年金積立金137兆円の運用を担うGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が株式に投資できる資産割合を12%から25%に引き上げること認めました。前々から話が出ていましたが、塩崎氏が厚労相になって一気に具現化しました。巨大資産を保有する公的な団体とも言えるGPIFが、日本企業の株式を買い支えするのですから、投資家は安心して日本企業の株を買うようになり、株価は上昇します。
塩崎氏が保有する株式23銘柄を元に、新潮が推計したところ、GPIFの投資割合が上がったことで、同氏は総額1285万9594円の“含み益”を上げたといいます。その「稼ぎ頭」が武田薬品(3630株保有)で、“含み益”は574万2660円だとも指摘しております。 話を単純化すると、塩崎氏はGPIFが大量の資産を株式市場に投入することを認めることによって、大企業を支え、自らもザクザク資産を増やしたということです。閣僚の株式投資は禁止されていませんから、別に悪いことではないんですが、なんだかなあ〜って感じ。個人的には、もう少し中小企業にも関心を持って欲しいです。製薬企業だって、がんばっているのは、武田だけじゃないですから。
で、写真は東京丸の内で。この方、すごいカメラ目線。写真慣れされている(^_^;)。おそらく今週末はサクラ満開!皆様、素敵な一週間をお過ごしください。
武田薬品の岩﨑真人取締医薬営業本部長が先週、製薬業界各紙のインタビューに応えて2月に発売した胃酸分泌抑制剤タケキャブの国内売上拡大に意欲を見せています。この領域の薬物治療は、現在、胃酸を出すプロトンポンプという部分を阻害するPPI阻害薬(Proton pump inhibitor)が主流ですが、タケキャブは既存品とは違う働きでプロトンポンプを阻害するP-CAB薬(Potassium-Competitive Acid Blocker : P-CAB)という新しいタイプです。

武田はタケプロンというPPI阻害薬のトップ製品を持っていますが、タケプロンの特許が切れ、後発品がわんさか出てきて市場を侵食されているので、タケプロンとは違うタイプのP-CAB薬である新薬タケキャブを出したのです。新薬ですから、当然、薬価は高いし、特許で守られるので、当面、後発品は出て来ません。安心して市場開拓ができます。
ところがタケキャブの承認申請で武田が提出したタケプロンとの比較試験の結果は「非劣性」。要するに、タケプロンと比べて「劣っていないけど、とくに優れてもいませんよ」ってことなんです。「ニュータイプの胃酸分泌抑制剤です!」ってプロモーションで押しまくれば、医師も「ちょっと使ってみっか」って感じになりましょうが、これってどうですか?
現在、PPI市場のトップ製品ネキシウムを持つアストラゼネカは2000年代初頭にP-CAB薬の開発を進めていましたが、ネキシウムとの比較試験の結果が「非劣性」だったので、「やってもしょうがない」と開発を中止した経緯があります。アストラゼネカ日本法人のガブリエル・ベルチ社長は武田のタケキャブも同じで、「PPIと比べて優位性がないのに一体、どこで使うの?」と疑問視しています。
胃酸分泌抑制剤はタケキャブの登場で激しいプロモーション合戦に突入します。かつて熾烈な宣伝合戦を繰り広げ、一線を踏み外した高血圧治療薬ブロプレス、ディオバンと同じ轍を踏まないようにメーカーのみならず、医師、メディアは要注意です。とくにメディア!!他人事だと思って、提灯記事ばっか書いてちゃダメですよ!変にケチ付ける必要もないけど。
で、写真は、武田(左、左から2番目が岩﨑氏)とアストラゼネカ日本法人(右、真ん中がベルチ氏)の会見風景。ではみなさま、満開の桜ももうすぐです。素敵な一週間をお過ごしください!
政府の規制改革会議が先週12日(木)に行った医薬分業に関する議論は、委員の発言に、思いつきや、準備不足が伺われる場面も多く、正直、物足りなさを感じました。とくに川渕孝一氏(東京医科歯科大大学院教授)には期待していましたが、冒頭で、誰も笑えないジョークらしき“つぶやき”を発したうえ、随分昔に書いた自著の宣伝を繰り返した印象が強く、がっかりしました。また、日本高血圧学会の理事で「まゆみとドクター森下のバイオレディオ」で、御馴染みの森下竜一氏(大阪大大学院教授)も「薬局に行ったら最新の薬が置いてなかった」などと、まさかの“イチ患者”発言(^_^;)、やはり高血圧の専門医としての医薬分業論を聞きたかったです。
しかし、「ついに医薬分業も新たなステージに来たんだなあ」と、感慨深くも思いました。議論全体のトーンが、医薬分業がいいとか、悪いとか、単純な二元論に陥ることなく、医薬分業が70%近くなった現状を認めたうえで「どうしたらもっと国民のためになる仕組みにできるのか」という建設的な方向で進められたこともよかったです。いわば、医薬分業の質的向上、改善論です。(その点において、土屋了介氏=神奈川県立病院機構理事長の発言が最も大人で深みがありました)
病院や診療所とは別の薬局と言う存在が間に入る以上、院外調剤のコストが院内調剤より高いのは当たり前ですが、そのコストが高すぎるのか。少ないのか。調剤料、調剤基本料、薬歴管理料、その他加算など、細切れになっている報酬はそれぞれ適切なのか。そこは大いに議論すべきです。ただ、ここは注意しないと、単に、医科と調剤のお金の分捕り合いになり、結果、医科にお金が移動しただけということになりかねません。
 それから医薬分業がなぜ始まったのか?規制改革会議の議論では正しい説明がありませんでした。その昔、病院、診療所が保険薬価より、滅茶苦茶安く医薬品を購入し、その差額を自分たちの収入にしていました。大きな差額が欲しいがために、患者を蔑にして、必要がない薬を使ったり、できるだけ差額が大きい薬を使ったりする傾向が一部にありました。メーカー、卸もある意味、そういう状況を黙認し、病院、診療所の“薬価差稼ぎ”に加担していました。それで旧厚生省が「これはいかん!病院、診療所から医薬品の購入を引きはがせ!」ってんで本格的に医薬分業推進に舵を切り、もう30年近く一心不乱に、病院、診療所、そして薬局に「薬価差で稼がなくても、医薬分業をすればお金が儲かりまっせ」と医療保険財源から出す報酬で誘導してきたんです。で、取り合えず病院、診療所からの薬の引きはがしは成功しました。が、一方で、医療保険という絶対つぶれない市場で、ほとんどリスクなく確実に稼げる調剤ビジネスの旨味に、目を付けたお金持ちの株式会社がドカドカ参入し、「魂なき調剤」を普及させた。で、時代遅れで、論理矛盾を来している継ぎ接ぎだらけの調剤報酬点数、そして調剤だけやって、あとは何にもしないロボットみたいな血の通わない変な薬局が沢山、出て来ちゃたんです。
それから医薬分業がなぜ始まったのか?規制改革会議の議論では正しい説明がありませんでした。その昔、病院、診療所が保険薬価より、滅茶苦茶安く医薬品を購入し、その差額を自分たちの収入にしていました。大きな差額が欲しいがために、患者を蔑にして、必要がない薬を使ったり、できるだけ差額が大きい薬を使ったりする傾向が一部にありました。メーカー、卸もある意味、そういう状況を黙認し、病院、診療所の“薬価差稼ぎ”に加担していました。それで旧厚生省が「これはいかん!病院、診療所から医薬品の購入を引きはがせ!」ってんで本格的に医薬分業推進に舵を切り、もう30年近く一心不乱に、病院、診療所、そして薬局に「薬価差で稼がなくても、医薬分業をすればお金が儲かりまっせ」と医療保険財源から出す報酬で誘導してきたんです。で、取り合えず病院、診療所からの薬の引きはがしは成功しました。が、一方で、医療保険という絶対つぶれない市場で、ほとんどリスクなく確実に稼げる調剤ビジネスの旨味に、目を付けたお金持ちの株式会社がドカドカ参入し、「魂なき調剤」を普及させた。で、時代遅れで、論理矛盾を来している継ぎ接ぎだらけの調剤報酬点数、そして調剤だけやって、あとは何にもしないロボットみたいな血の通わない変な薬局が沢山、出て来ちゃたんです。
こういう時代背景、医療環境、政策面での流れを厚労省はなぜ、説明しなかったのでしょうか?せっかく、規制改革会議が公開の場で議論のテーマに載せたのです。「医薬分業は患者にとっていいことです」なんてきれいごとだけ言ってごまかすのはまずいでしょう。過去の政策の意図、その成否、現状の問題点を国民にしっかり伝えるべきです。じゃないとしっかりした議論ができない。
写真は都営大江戸線、赤羽橋付近。通りがかりにふと、見上げたら東京タワー!!堂々のお姿。遠くから眺めると、いいですね。中はどうってことないけど(^_^;)。それから有楽町のガード下。「貝」「馬」そしてかなたに「牛」いい感じです。春目前の都内の夜景でした!ではみなさま、素敵な一週間をお過ごしください。気が付けばもう3月中旬、満開の桜がもうすぐですね!
 みなさん、お元気ですか?休み明けの月曜日は静かな薄曇りでスタートを切りました。街中を舞っていた花粉も湿気で地に落ち、ゆったりした佳い滑り出しです。
みなさん、お元気ですか?休み明けの月曜日は静かな薄曇りでスタートを切りました。街中を舞っていた花粉も湿気で地に落ち、ゆったりした佳い滑り出しです。
さて、製薬企業のMR(医薬情報担当者)の現状を数年ぶりに取材し、医薬経済3月1日号に記事を書きました。ここ10数年、MRを巡る報道は「このままじゃダメだ」「いらなくなる」と悲観論ばかりですが、もうウンザリ。現場のMRに苦言を呈するのは簡単ですが、果たしてそれで、なんか変わるでしょうか?MRは一企業の一情報担当者ですから、個々人ではどうしようもない限界もあるでしょう。少なくとも各社の人事戦略担当のマネジメントが変革の必要性を認識して、戦略、評価体系を改めなきゃどうしようもないことが多いはずです。展望なきMR叩きは、もうやめませんか?そんな思いを込めて執筆しました。
取材過程で、製薬企業の依頼を受けてMR活動を実施するCSO(営業受託業)のコントラクトMRが増えていることを再認識しました。09年は1769人だったのが今は5000人くらいまで膨らんでいます。しかし、日本のMR総数は6万5000人ですから、7%強です。採用は製薬企業外の営業経験者がほとんどだから、MR経験者の受け皿にはならないでしょう。コントラクトMRが世界で最も多い英国ですら全MRの25%ですから、製薬企業の外部委託は、やはり一部に過ぎずコアの部分はしっかり自社のMRが支えています。ですから今、日本でコントラクトMRが増えていると言っても間違いなく、いつか頭打ちになります。
CSOも、成長のために新たなビジネスモデルを作っていかねばなりません。現時点では、クライアントとなる製薬企業の看板を背負った営業マンの域を出ていない。製薬企業ではなく、医療機関を顧客にした受託ビジネスはいかがでしょうか?医薬情報のプロとして、病院薬剤部との間に立って、各社のMRが持ってくる情報を精査し、適正な薬剤選択を支援するのです。そういうの是非やって欲しいです。しかし、個々の病院は製薬企業ほどお金持っていませんから、収益面で難しいでしょうか?
で、写真は2月24日、品川で開かれたMR認定センターのミーティング。各社のMR教育研修担当者がズラリ。数年ぶりに取材させていただきましたが、テーマに、とくに大きな変化はありませんでした。個人的には、もう少し核心に迫る議論が欲しいです。それでは皆様、素敵な一週間をお過ごしください!
【お知らせ】米ニューヨークを拠点に医療、製薬情報を発信するMSAパートナーズの出版部門ブルームース・リサーチが「2014年製薬業界の動向―2015年に向けて―」を発刊した。これまで蓄積したグローバル情報を元に、製薬業界のトレンドを解説。研究開発、マーケティング、公的規制の動きを独自の視点で詳細に分析している。また、時価総額上位18社と、株式非公開3社計21社の全貌をコンパクトにまとめた。全74ページ、価格は2,500ドル。詳細は以下のURL=http://msapr.com/main2/jp/resources-blue-moose-research.html
 みなさんお元気ですか?寒気の波間波間に、ちょっとだけ春の気配を感じる今日この頃です。己(オノレ)は風邪気味で、先週後半、活動を緩めました。皆さんもお気を付けください。
みなさんお元気ですか?寒気の波間波間に、ちょっとだけ春の気配を感じる今日この頃です。己(オノレ)は風邪気味で、先週後半、活動を緩めました。皆さんもお気を付けください。
さて後発医薬品。各社の努力で「ジェネリック医薬品」という呼称がすっかり定着しましたね。しかし、ジェネリックの意味を正しく理解している患者さんは、まだまだ少ないのではないでしょうか?
新潟薬科大学薬学部の上野和行先生が3月25日のセミナーで「先発品と成分は同じだけど、コーティングなど、着ている服が違う医薬品」と定義していました。「着ている服が違う」っていうのは、絶妙な表現です。これなら患者に分かりやすく伝わると思います。さらに、ジェネリックは、先発品が出てから、概ね10年以上経過してから出るので、着る「服」のデザインも最先端。先発品より飲み易くしたり、劣化しにくくしたり、数々の利点が付与された「リニューアル医薬品」だとも強調しました。確かに一理ありますね。 ただ、いま市場に出ているジェネリックの何パーセントが「リニューアル医薬品」と呼べるのか。調査はないようで、今のところ何とも言えないのが実情です。
一方、「リニューアル医薬品」でないジェネリックは、先発品と同程度のランクのデザインの「服」を着ているが、価格が安い。「コスト抑制型医薬品」とでも呼びましょうか? ジェネリックは基本的に「先発品と着ている服が違う医薬品」ですが、例外的に全く同じ服を着ている場合もあります。先発品企業が自社のブランド製品について、他社に後発品として製造販売することを認める「オーソライズド・ジェネリック(AG)」です。ですから、ジェネリック医薬品は、いま大きく3つに分かれる。「AG」「リニューアル医薬品」「コスト抑制型医薬品」です。3つのうち、どの戦略で行くかは、各社の判断です。 いずれにせよ、ジェネリックに対する患者の認知度は、かなり上がってきました。もう一歩進んだ理解を求める段階に入ったと言えそうです。
で、写真は東京駅丸の内南口。取材の合間に丸善に。溢れるような新刊を前にすると、ついつい時間が経つのを忘れて、「知の森林」でフィールドワークに浸ってしまいます。というわけで、皆さま。季節の変わり目です。お体に気を付けて!充実した素敵な一週間をお過ごしください。
【お知らせ】米ニューヨークを拠点に医療、製薬情報を発信するMSAパートナーズの出版部門ブルームース・リサーチが「2014年製薬業界の動向―2015年に向けて―」を発刊した。これまで蓄積したグローバル情報を元に、製薬業界のトレンドを解説。研究開発、マーケティング、公的規制の動きを独自の視点で詳細に分析している。また、時価総額上位18社と、株式非公開3社計21社の全貌をコンパクトにまとめた。全74ページ、価格は2,500ドル。詳細は以下のURL=http://msapr.com/main2/jp/resources-blue-moose-research.html
 ドラッグストアの処方せん調剤。滅茶苦茶ですね。患者が来て、処方せんを見て、医師が出した処方に間違いはないか。過去に飲んだ薬との間で何か問題はないか。それをチェックするのが本来の保険薬局の役割なのに。ツルハの子会社「くすりの福太郎」、イオン傘下の「CFSコーポレーション」は、薬剤服用歴(薬歴)を作っていなかったというのですから。福太郎は17万件、CFSは7万件も。端っからやる気がないんでしょうね。やっていないのに、調剤報酬だけは、しっかり請求している(^_^;)。これぞ、まさしく「やらずぶったくり」の王道。「やった、やった詐欺」。ジャーナリストで言えば取材しないで記事を書くインチキをするようなもんです。有りえないことです。呆れて物が言えません。
ドラッグストアの処方せん調剤。滅茶苦茶ですね。患者が来て、処方せんを見て、医師が出した処方に間違いはないか。過去に飲んだ薬との間で何か問題はないか。それをチェックするのが本来の保険薬局の役割なのに。ツルハの子会社「くすりの福太郎」、イオン傘下の「CFSコーポレーション」は、薬剤服用歴(薬歴)を作っていなかったというのですから。福太郎は17万件、CFSは7万件も。端っからやる気がないんでしょうね。やっていないのに、調剤報酬だけは、しっかり請求している(^_^;)。これぞ、まさしく「やらずぶったくり」の王道。「やった、やった詐欺」。ジャーナリストで言えば取材しないで記事を書くインチキをするようなもんです。有りえないことです。呆れて物が言えません。
で、まずは何を優先すべきか。当事者を徹底的に厳しく叩き、処分することです。これは、ほとんど犯罪行為ですから。一般的に、根本的な倫理を踏みにじって起きた犯罪に対して「みんなで考えましょう」「私も自分のこととして考えます」って言いますか?言わないでしょう。だからまずは当事者の問題なのです。そして次はドラッグストア協会。これを機に、ドラッグストアでの調剤はどうあるべきか。もう一度、徹底的に議論し、再発防止について考えるべきです。
調剤ビジネスには、大手チェーン、ドラッグストア、中小個人薬局と大きく3つの業態がありますが、国民には、どうでもいいこと。全く知られていない。だから今回のことで、十羽一絡げにマイナスイメージを抱くかもしれません。それをどう払しょくするか。そこが日本薬剤師会の役割だと思います。己(オノレ)はまじめにやっている薬局が沢山あるのを知っています。確かにサービスの不十分さはあるにしても。。本質がどこにあるか。曖昧にしたまま情緒的なムードだけが先行し、マイナスイメージが膨張していく社会は、不健全です。どこに本質があるのか。見極める能力を無くした社会は、歪んでいきます。
写真は日比谷の、とあるレトロな喫茶店で。取材の合間に時間ができたので、コーヒータイム。なかなか風情があるところでした(*^_^*)では皆様、充実した素晴らしい一週間をお過ごしください!
 日本の製薬業界も本格的なスリム化時代に突入したようです。14年以降、複数の企業が希望退職を募集。アステラス製薬430人、第一三共513人、ノバルティスファーマ日本法人450人、グラクソ・スミスクラン日本法人200~400人、サノフィ日本法人200~300人と、この5社だけで最大2000人以上の人材が所属企業を離れます。
日本の製薬業界も本格的なスリム化時代に突入したようです。14年以降、複数の企業が希望退職を募集。アステラス製薬430人、第一三共513人、ノバルティスファーマ日本法人450人、グラクソ・スミスクラン日本法人200~400人、サノフィ日本法人200~300人と、この5社だけで最大2000人以上の人材が所属企業を離れます。
みんな一流企業ですから、もちろん十分な積み増し退職金が支払われます。しかし、「一つの企業で一生、勤め上げる」という“日本型雇用形態”の崩壊の足音が製薬業界にもヒタヒタと迫ってきているようです。しかし、己(オノレ)は、これをマイナスだと考えていません。現状に不満で、自信がある人材はどんどん飛び出して、業界を引っ掻き回し、活性化させて欲しいと思います。所属企業を離れる2000人の皆様!己は期待しております。どうか心身を健全に保ち、がんばってください!!
で、写真は都内高級ホテル。ではありません!青山にある山王メディカルセンター。列記とした病院のロビーでございます。すんげえ内装。静かにクラッシックのBGMが流れていて、高級感が漂います。差額ベット代。いくらするんだろうか?お高いんでしょうね。きっと^_^; ということで、皆さま。充実した素敵な一週間をお過ごしください!!
 みなさんお元気ですか?米ファイザーがホスピーラを買収することになりましたね。ファイザーは昨年、アストラゼネカの買収に失敗しましたが、事業再編への意欲は失っていなかったんです。しかし、AZ買収頓挫から1年も経ずして、ホスピーラ買収。一つの戦略が駄目ならすぐに次の矢を放つ!!!このスピードたるや目を見張るものがあります。
みなさんお元気ですか?米ファイザーがホスピーラを買収することになりましたね。ファイザーは昨年、アストラゼネカの買収に失敗しましたが、事業再編への意欲は失っていなかったんです。しかし、AZ買収頓挫から1年も経ずして、ホスピーラ買収。一つの戦略が駄目ならすぐに次の矢を放つ!!!このスピードたるや目を見張るものがあります。
さてホスピーラの日本法人、ホスピーラ・ジャパンの行方やいかに?2004年設立ですから、わずか10年ちょいの歴史しかない。従業員も約100人で決して大きくありませんが、今後の情勢が業界に与えるインパクトは決して小さくない。ファイザー日本法人は昨年、新薬部門を切り離して「ファイザー製薬」を創設。一方で、ジェネリック事業は元の日本法人「ファイザー」に残っています。ホスピーラの基盤は注射剤ジェネリックですから、おそらくホスピーラ・ジャパンは「ファイザー」と、くっ付くことになるでしょう。社内はしばらく落ち着かない状態になると思われますが、従業員のみなさま。自分を失わないよう、行く末を見つめて、しっかりがんばってください。
翻って国内企業。少なくとも国内企業同士の合併の動きは表面化していません。相変わらずアステラス製薬と第一三共の合併の噂は消えませんが、「アステラスが、いまのままの第一三共と一緒になっても、足を引っ張られるだけ」(証券アナリスト)との情勢分析が主流で、現実性は低いままです。ただ、ここに来て新たな噂が浮上してきました。協和発酵キリンが合併の相手を探していて、武田薬品が名乗りを上げているというもの。飽くまでも噂ですが、実現すれば、明るい話になると思いませんか?
写真は米ファイザーの会長兼CEO、イアン・リード氏。最近、流行りの経済学者トマ・ピケティ氏によると米国ではトップ10%の人が、国全体の富の70%を保有しているといいます。リード氏は間違いなく、その10%に入るでしょうね。それではみなさま、素敵な一週間をお過ごしください!!!