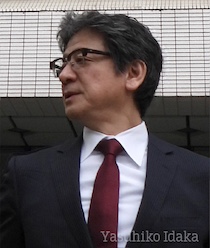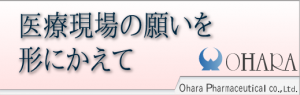◆MeijiSeikaファルマの小林大吉郎代表取締役社長
MeijiSeikaファルマが、細胞内でmRNAが自己増殖する技術を応用し、少量投与で効果が長持ちする新型コロナウイルス感染症対応、次世代ワクチン「コスタイベ」の承認を世界で初めて取得した。小林大吉郎代表取締役社長は11月28日の記者会見で「“ワクチン敗戦”と揶揄された我が国であるが、レプリコン(自己増殖型mRNA)の実用化では、日本が世界に一歩先んじている」と述べ、コスタイベを起点とした事業発展に意欲を示した。ただ、今回の承認は「起源株」で、現在流行している「XBB1.5株」などに対応する一部変更申請、承認はこれから。供給は24年度下期の予定だ。移ろいやすい新型コロナの感染状況をいかに見極めて準備を進めるかが、収益のカギを握る。

◆内閣官房参与・鴨下一郎氏
総理大臣の“ブレーン”的な役割を担う内閣官房参与、鴨下一郎氏【写真】に創薬力強化に向けた今後の医薬品産業政策についてお話を伺った。
鴨下氏は医学博士で元環境相。衆院厚労副大臣、厚労委員長などを歴任し、社会保障、健康・医療、関連産業の施策に明るい。21年10月に9期28年の衆院議員を引退、23年9月、健康・医療戦略を担当する内閣官房参与に任命された。「創薬、認知症に関して助言を行う参与として適任」と岸田文雄総理が抜擢した。24年度以降の医薬品産業政策をまとめあげる「総合調整役」として最も注目されるキーマンだ。
鴨下氏は「日本の創薬力に陰りが出ている」と憂慮、薬価制度などを通じた産業構造改革の必要性を強調した。今後の政策提案については「関連するステークホルダーによっては、多少、眉を顰めるようなことがあるかもしれない」と述べた。以下、速記メモを元に一問一答形式で概略をお伝えする。
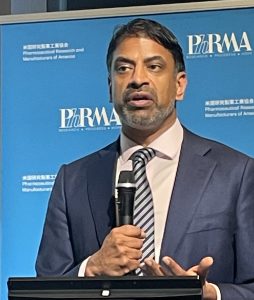
◆米国研究製薬工業協会(PhRMA)のヴァス・ナラシンハン会長
米国研究製薬工業協会(PhRMA)のヴァス・ナラシンハン会長(ノバルティスCEO)が来日し、11月9日、記者会見を開いた。PhRMA会長は例年、この時期、「PhRMA Days」と称して来日し、数日間、日本に滞在。政府関係者などを訪問し、米国業界の要望を訴える。今回は会見前日の8日に、岸田文雄総理大臣、武見敬三厚労大臣に接見、好感触を得たようだ。会見の内容については、すでにPhRMAが同日レポートを発信している。このうえ会長の発言を、聞いたままダラダラ書き連ねても、読者の貴重な「可処分時間」を無駄使いさせるだけで、SDGsにそぐわないので、詳細はPhRMA発レポート、資料に譲る。薬新プラザでは、私が記者会見で、気づいたこと、考えたことに焦点を絞って簡潔に記す。
【11月6日発】早期AD薬ドナネマブの試験は「投薬の止め時」を明確化し、「タウ蓄積の影響」を考慮した点が“斬新”! ※見出し及び本文中の医薬品名に誤りあったため修正致しました(11月8日23時30分)

◆イーライリリーのダニエル・スコブロンスキー最高科学・医学責任者(10月10日のセミナーにて)
日本イーライリリーが9月に日本で承認申請した早期アルツハイマー型認知症(AD)の進行遅延薬ドナネマブは臨床試験で「投薬を止める時期」を明確に示した。また、試験をデザインする際に、ADの根本要因とされるアミロイドβ(以下、Aβ)凝集体のみならず、疾患の悪化速度に影響するタウの蓄積を考慮した。「投薬を止める時期」「タウ蓄積の影響」を試験に組み込んで結果を出したのは斬新だ。試験の背景、内容を分かり得た範囲でレポートする。

◆沢井製薬・沢井光郎会長
沢井製薬が九州工場で製造していた胃潰瘍治療薬テプレノンカプセルで、長期に渡って不正な溶出性試験を実施していた事実が発覚した。溶出性試験は、販売後の医薬品が服用者の体の中でしっかり溶けて効能、効果を問題なく発揮するかどうか、数年毎に確認する試験。厚労省の省令(GMP)で企業に精密な実施が義務付けられている。試験結果で、溶け具合(溶出性)が基準値を極端に下回ること(OOS=OUT OF SPECIFICATION)がわかったら、本来の効能・効果を発揮せず、治療に影響を及ぼしかねないので、使用期間内でも回収などの対応が必要になる。OOSは、カプセルの経年劣化が影響して発生することが多い。沢井は、そのカプセルを比較的新しいモノに替えて試験を実施していた。主要成分(内容物)を、比較的新しいカプセルに詰め替えれば、溶出性は維持できて当たり前で明らかなGMP違反だ。沢井は、テプレノンでそれをやっていた。

◆沢井製薬・木村元彦社長
沢井は「同様の事案は、テプレノン以外の製品にはない」と説明、すでに全ロット回収し、今のところ健康被害報告はない。
ただ、小林化工、日医工の不正発覚以降、後発医薬品各社の製品回収、限定出荷が続出。行政処分が次々に下され、国民の不信感は増幅している。例え、販売後の劣化を確認する溶出性試験で、それが一製品に止まっていたにせよ、後発品業界トップ3に名を連ねる沢井で不正が発覚したのだから、社会的な衝撃は大きい。信頼を回復するには、相当の時間を要するだろう。一体なぜ、こんな不正が起き、しかも長期間続いたのかーー。沢井が10月23日に発表した特別調査委員会の報告書を読むと、その原因の一端が見えてくる。

◆MR認定センターの記者会見風景、左から近澤洋平専務理事・事務局長、小日向強企画部長、楳坂宏試験事業部長
公益財団法人MR認定センターが10月25日、記者会見し、2026年の制度改革に向けた取り組みについて説明した。近澤洋平専務理事・事務局長は「薬物療法の高度化、専門化、個別化が急速に進み、従来の教科書には載っていないものも出てきている。一方、医薬品の承認審査も迅速化され、市販後の情報収集・提供の重要性が増している」とMRを取り巻く環境が大きく変化している現状を強調。そのうえで「当センターは、公益財団法人だ。その観点から今の制度は“公益性”“公正性”を担保できているか。今一度、再検証し、時代の変化に適応する見直しを進める」と意欲を見せた。